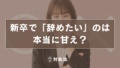- 朝、目が覚めると、体が鉛のように重い…
- 会社に行くことを考えると、吐き気がする…
- 仕事に行きたくない…でも、休むわけにはいかない…
新卒で入社したばかりなのに、すでに「仕事行きたくない病」にかかってしまっている…。
そんな悩みを抱えていませんか?
「仕事に行きたくない」と思うのは、決してあなただけではありません。
多くの新卒者が、同じような悩みを抱え、苦しんでいます。
- 新卒が「仕事行きたくない病」になる原因
- 「仕事行きたくない病」の症状チェックリスト
- 「仕事行きたくない病」を克服する方法
- 専門家のサポートが必要な場合
- 退職代行サービスという選択肢について
この記事では、新卒が「仕事行きたくない病」になる原因を解明し、具体的な克服方法を7つご紹介します。
さらに、専門家のサポートが必要な場合や、最終手段としての退職代行サービスについても解説します。
あなたの「仕事行きたくない」気持ちを解消し、前向きに仕事に取り組めるようになるためのヒントが、きっと見つかるはずです。
なぜ「仕事行きたくない病」になる?新卒特有の原因

新卒者が「仕事行きたくない病」になってしまうのには、いくつかの原因が考えられます。
新卒特有の原因としては、主に次の4つが挙げられます。
1.理想と現実のギャップ。仕事内容・人間関係・労働時間
- 想像していた仕事と全然違う…
- 上司や先輩と、どうしても合わない…
- 毎日残業ばかりで、自分の時間が全くない…
入社前に抱いていた理想と、現実とのギャップは、新卒者を「仕事行きたくない病」に陥れる大きな要因です。
仕事内容のギャップ
「やりがいのある仕事ができる!」と思って入社したのに、実際は雑務ばかりでモチベーションが下がることも。
営業職ならお客様と直接商談するはずが、実際は電話をかけ続ける日々。
企画職なら新しいアイデアを生み出す仕事だと思っていたのに、資料作成や上司のサポート業務ばかり。
クリエイティブな仕事も、自由な発想を活かせる場面は少なく、決められたルール通りに作業をこなすだけ。
「こんなはずじゃなかった…」と感じる瞬間が増えていきます。
人間関係のギャップ
働く上で「人間関係」は大きな影響を与えます。
特に新卒のうちは、上司や先輩に相談しながら仕事を覚えていくもの。
しかし、威圧的な上司や冷たい先輩に囲まれていると、質問すらしにくくなり、仕事のミスが増えてしまうことも。
同僚との価値観が合わないと、職場で孤立してしまい、精神的な負担が大きくなります。
「仕事は好きだけど、人間関係がつらい…」という状況に悩む人も少なくありません。
労働時間のギャップ
「ワークライフバランスを大切にできる職場」と聞いていたのに、実際に働いてみると毎日残業続き。
繁忙期だけかと思いきや、慢性的に長時間労働が続くケースもあります。
さらに、休日出勤が当然のように求められたり、有給休暇が制度としてはあっても、周りの空気的に取得しにくい…といった状況も。
「働くために生きているのか?」と思うほど、自分の時間が取れず、どんどん疲弊してしまいます。
新しい環境への不適応 ? 慣れない環境とプレッシャー
新しい環境への不適応も、「仕事行きたくない病」の原因となります。
学生から社会人になり、生活リズムや人間関係、仕事の進め方など、あらゆる面で変化が起こります。
これらの変化に、心身がついていけず、ストレスを感じてしまうのです。
自己肯定感の低下。失敗経験や周囲との比較
初めての仕事で失敗したり、周りの人と比べて落ち込んだりすることで、自己肯定感が低下し、「仕事行きたくない病」につながることがあります。
特に、真面目で責任感の強い人ほど、自分を責めすぎてしまいがちです。
燃え尽き症候群(バーンアウト)入社前の頑張りすぎ
入社前から、就職活動や内定者課題などを頑張りすぎて、入社後に燃え尽き症候群(バーンアウト)になってしまうケースもあります。
目標を達成したことで、心身ともに疲弊し、仕事への意欲を失ってしまうのです。
「仕事行きたくない病」の症状チェックリスト

もしかして、私も『仕事行きたくない病』かも…?
そう感じたら、まずは、以下のチェックリストで自分の状態を確認してみましょう。
身体的症状
- [ ] 体がだるい、疲れやすい(倦怠感)
- [ ] 頭痛やめまいがする
- [ ] 夜、なかなか寝付けない、眠りが浅い(不眠)
- [ ] 食欲がない、または、過食してしまう
- [ ] 動悸や息切れがする
- [ ] 便秘や下痢をしやすい
- [ ] 肩こりや腰痛がひどい
精神的症状
- [ ] 気分が落ち込む、憂鬱になる
- [ ] 何事にも興味が持てない、やる気が出ない(無気力)
- [ ] 不安や焦りを感じる
- [ ] イライラしやすい
- [ ] 集中力や記憶力が低下する
- [ ] 自分を責めてしまう
- [ ] 将来に希望が持てない
具体的なメンタル不調のサインについては【見逃し厳禁!新卒が発するメンタル不調サインとSOS】の記事で詳しく解説しています。
行動の変化
- [ ] 遅刻や欠勤が増える
- [ ] 仕事でミスが増える
- [ ] 人との関わりを避けるようになる
- [ ] 趣味や好きなことを楽しめなくなる
- [ ] 服装や身だしなみに気を遣わなくなる
- [ ] 部屋に引きこもりがちになる
- [ ] アルコールや薬物に依存するようになる
これらの症状が複数当てはまり、2週間以上続く場合は、「仕事行きたくない病」の可能性があります。
早めに対処することが大切です。
「仕事行きたくない病」を克服する7つの方法

「仕事行きたくない病」を克服するためには、心身の健康を整え、ストレスを軽減し、仕事へのモチベーションを高めることが重要です。
ここでは、具体的な7つの方法をご紹介します。
1.質の高い睡眠を確保する。寝具・睡眠時間・生活習慣
「睡眠不足は万病のもと」と言われるように、質の高い睡眠は心身の健康に不可欠です。
質の良い睡眠をとるためには、寝具の見直しや生活習慣の改善が大切です。
まず、自分に合った枕やマットレスを選ぶことで、体への負担を減らし、快適な睡眠環境を整えましょう。
また、毎日7~8時間の睡眠時間を確保することも重要です。
さらに、生活習慣を整えることも良質な睡眠につながります。
就寝・起床時間を一定にすることで、体内リズムが整い、スムーズに眠りにつきやすくなります。
寝る前にスマホやパソコンの画面を見ると、ブルーライトの影響で眠りが浅くなるため、できるだけ控えましょう。
また、カフェインやアルコールの摂取は睡眠の質を低下させるため、就寝前は避けるのが理想的です。
さらに、日中に適度な運動を取り入れることで、夜ぐっすり眠る助けになります。
こうした工夫を取り入れることで、より良い睡眠を得られるようになります。
2.適度な運動を取り入れる。ウォーキング・ストレッチ・ヨガ
適度な運動は、ストレス解消や気分転換に効果的です。
激しい運動をする必要はありません。
無理のない範囲で、継続できる運動を選びましょう。
ウォーキング
ウォーキングは、気軽に始められる運動のひとつ。
通勤や買い物のついでに少し遠回りして歩いたり、公園や川沿いを歩くのもおすすめです。
適度な運動になるだけでなく、外の景色を楽しむことでリフレッシュにもつながります。
ストレッチ
ストレッチは、体をほぐしてリラックスするのに最適。
朝に行うと血流が良くなり、スッキリ目覚められます。
寝る前に行うと、体の緊張がほぐれて眠りやすくなる効果も。
無理に伸ばさず、気持ちいいと感じる範囲で行うのがポイントです。
ヨガ
ヨガは呼吸を意識しながら体を動かすことで、心と体のバランスを整える効果があります。
仕事や勉強で疲れたときに、ゆっくりとヨガのポーズをとると、気持ちが落ち着いてリラックスできます。
自宅で動画を見ながら行うのも手軽でおすすめです。
3.バランスの取れた食事。栄養バランス・食事時間
バランスの取れた食事は、健康を維持するためにとても大切です。
「忙しい朝は菓子パンとコーヒーだけ」なんて生活を続けていると、そりゃあ体調も気分も優れませんよね。
脳と体の燃料となる食事は、実は気分の安定にも大きく関わっています。
栄養バランスを意識しながら、食べる時間や食べ方を工夫することで、体調が整い、気分も安定しやすくなります。
栄養バランス
食事は、炭水化物(主食)、たんぱく質(主菜)、ビタミンやミネラル(副菜)をバランスよく摂ることが大切です。
特定の栄養素に偏ると、体調不良や疲れやすさの原因になることも。
特に野菜不足は気分の落ち込みに直結することも。
冷凍野菜やカット野菜を活用するのも一つの手です。
忙しいときでも、野菜やたんぱく質をしっかり摂れる食事を意識しましょう。
食事時間
食事の時間がバラバラだと、体内のリズムが乱れ、消化や代謝にも影響が出ることがあります。
朝・昼・夜とできるだけ決まった時間に食べることで、胃腸の調子を整え、エネルギー補給のタイミングも安定します。
特に、朝食を抜くのはNGです。
朝食をしっかり食べることで、1日のエネルギーをチャージし、仕事への集中力を高めることができます。
よく噛んで食べる
食べるときによく噛むことで、満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎを防ぐことができます。
満腹中枢を刺激して食べ過ぎを防ぐだけでなく、リラックス効果もあるんです。
昼食時はついつい急いで食べがちですが、少しだけゆっくり味わってみてください。
また、よく噛むことで消化がスムーズになって胃腸の負担も軽減。
早食いをすると満腹感を得る前に食べ過ぎてしまうため、意識してゆっくり食べることが大切です。
4.趣味やリフレッシュの時間を作る。好きなことや没頭できること
仕事以外の時間で、趣味やリフレッシュの時間を意識的に作りましょう。
- 好きなこと: 映画鑑賞、読書、音楽鑑賞、スポーツ、旅行など
- 没頭できること: ゲーム、プラモデル作り、手芸、料理など
好きなことや没頭できることに取り組むと、ストレスを発散して気分転換につながります。
5.信頼できる人に相談する ? 家族、友人、先輩、カウンセラー
悩みを抱え込んでしまうと、どんどん気持ちが沈んでしまうことがあります。
そんなときは、一人で抱え込まずに信頼できる人に相談してみましょう。
話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になったり、新たな視点に気づけたりすることがあります。
家族
家族は、あなたのことを一番よく知っている存在です。
気持ちを素直に話しやすく、精神的な支えになってくれることも多いでしょう。
特に人生経験が豊富な親や兄姉なら、客観的なアドバイスをくれることもあります。
友人
友人は、気軽に話せる心強い存在です。
特に同じような悩みを経験している友人なら、共感してくれたり、一緒に解決策を考えてくれたりするかもしれません。
仕事の悩みなら、同僚と話すことで「自分だけじゃないんだ」と安心できることもあります。
先輩
職場の先輩は、同じ環境で働いているからこそ、より実践的なアドバイスをくれる存在です。
自分が悩んでいることをすでに経験している先輩も多いため、解決のヒントをもらえることも。
困ったときは遠慮せずに相談してみましょう。
カウンセラー
家族や友人には話しにくい悩みがあるときは、専門的な知識を持つカウンセラーに相談するのも一つの方法です。
第三者の視点から冷静にアドバイスをもらえるため、気持ちが整理されることも。
必要に応じて、適切なサポートを受けることも考えてみましょう。
6.目標設定と達成感。小さな目標と成功体験
仕事に行きたくない気持ちを変えるには、小さな成功体験の積み重ねが効果的なんです。
達成感って、心を動かす原動力になりますよね。
大きな目標だと挫折しやすいので、まずは「今日一日」という単位で考えてみましょう。
「この資料、今日中に半分まで終わらせる」など、具体的かつ達成可能な目標なら、クリアする喜びを味わえます。
そして、小さな成功体験が、次第に仕事への前向きな気持ちにつながっていくんです。
7.環境を変える。部署異動や転職
どうしても今の環境が合わないと感じる場合は、環境を変えることも選択肢の一つ。
逃げではなく、自分の可能性を広げる前向きな決断と考えましょう。
会社内での部署異動は、比較的ハードルが低い選択肢。
違う仕事内容や職場環境に変わるだけで、気持ちがリフレッシュすることもあります。
「今の部署より営業の方が合いそう」「もっとクリエイティブな部署で力を発揮したい」など、自分の強みや適性を考えながら検討してみてはいかがでしょうか。
改善しない場合は専門家のサポートも検討しよう

上記の7つの方法を試しても「仕事行きたくない病」が改善しない場合は、専門家のサポートが必要な可能性があります。
心療内科・精神科の受診
長引く「仕事行きたくない病」の背景には、うつ病や適応障害といった心の病気が潜んでいることも。
こういった病気は自分の努力だけではどうにもならないもので、専門的な治療が必要です。
心療内科や精神科を受診するのは、ちょっと勇気がいるかもしれませんね。
でも、早めの受診が早期回復につながります。最初は「心が疲れているので相談したい」と伝えるだけでOK。
医師は話を丁寧に聞いて、あなたの状態に合った対応をしてくれます。
カウンセリングで悩み相談や心理療法
医師の診察とは別に、カウンセラーとの定期的な面談も効果的です。
第三者に話を聞いてもらうことで、自分でも気づかなかった思考パターンや問題の原因が見えてくることがあります。
特に認知行動療法などの心理療法は、「仕事行きたくない」という気持ちの裏にある考え方や感情に働きかけ、より健全な思考パターンを身につける手助けをしてくれます。
「どうせ私なんて…」という自動思考を「まずは今日できることからやってみよう」という建設的な思考に変えていくプロセスは、とても勇気づけられるものですよ。
涙が出るほど辛い…そんな時の具体的な対処法については【新卒で「会社行くのが辛い、涙が出る…」原因と今すぐできる対処法】の記事で解説しています。
休職制度の利用して心身の回復
もう限界を感じているなら、休職という選択肢も考えてみましょう。
無理を重ねて倒れてしまうより、一度立ち止まって充電する時間を作ることが、長い目で見ると賢明な場合もあります。
医師の診断書があれば、多くの会社では休職が認められます。
休職中は心と体のケアに専念できますし、距離を置くことで「本当に自分がしたいこと」が見えてくることもあるんです。
退職代行サービスで仕事を辞める

どうしても会社を辞めたいけど、「自分から言い出せない…」「退職を伝えたら、何を言われるか分からない…」
といった状況で、精神的に追い詰められてしまった場合は、退職代行サービスという選択肢もあります。
あなたに代わって退職の意思を会社に伝えてくれるサービスで、直接の対面をせずに退職手続きを進められます。
ただ、費用がかかる、会社との関係が悪化する可能性もあるため、最終手段として考えるのが良いでしょう。
あなたの心身の健康を守るためなら、検討する価値はあります。
まとめ
新卒で「仕事行きたくない病」に陥るのは、本当によくあることです。
あなただけじゃないんですよ。
多くの新社会人が、理想と現実のギャップや新しい環境への不適応、自己肯定感の低下などに悩んでいます。
大切なのは、「これは成長過程の一部」と捉え、一人で抱え込まず早めに対処すること。
今回ご紹介した方法の中から、あなたに合ったものを見つけて少しずつ試してみてください。
誰にでも、つらい時期はあります。
でも、必ず乗り越えられます。
あなたが「仕事行きたくない病」を克服し、充実した社会人生活を送れることを心から願っています!